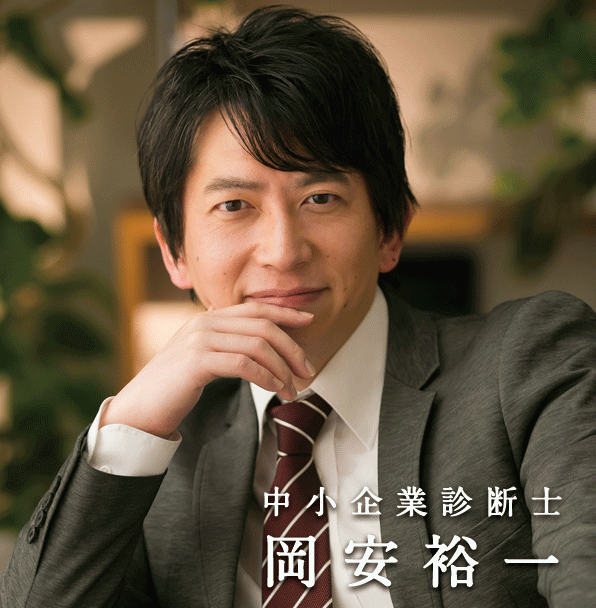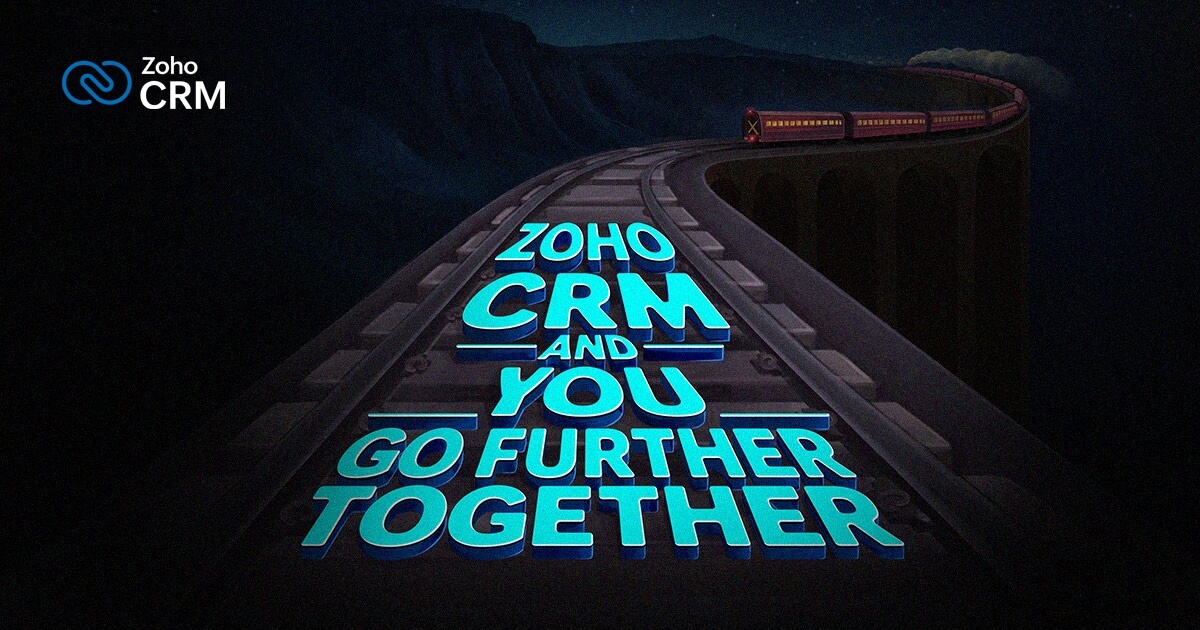営業活動は属人化が進み、営業担当者以外は把握できないことが多くなり、スキルや経験によって差が広がっています。しかし、購買行動の変化により、属人化した営業活動では成果をあげにくくなっているのが現状です。そこで属人化を解消するために取り組んでいるのが「営業プロセスの見える化」です。
営業プロセスの見える化とは何でしょうか?また、メリットや見える化を行うための手順はどのようなものがあるのでしょうか?
この記事では営業プロセスの見える化とメリットや見える化の手順を解説します。
営業プロセスの見える化とは
まずは「営業プロセス」と「営業プロセスの見える化の必要性」について解説します。
営業プロセスとは
「営業プロセス」とは、見込み客との最初の接点から受注、アフターフォローに至るまでの営業活動を構成する一連のプロセスです。具体的には「見込み客獲得→ナーチャリング→商談→受注→フォロー」などのプロセスです。
- 見込み客獲得ウェブサイト・セミナー・キャンペーン
電話
メール - ナーチャリングメールマガジン
- 商談商談
提案
見積 - 受注契約
納品 - フォローフォロー
アップセル
クロスセル
「BtoBかBtoCか」「プロダクト販売かサービスの提供か」などによって営業プロセスは多少異なりますが、多くの場合は上記のような工程となります。また、大企業などでは見込み客獲得はマーケティング部門の役割として定義されていますが、マーケティング活動に専門の人間を割くことができないところは営業部門の役割の1つとして定義している会社もあります。
営業プロセスの見える化の必要性
近年では、CRMやSFAなどの営業活動に関連するITツールが普及するにつれ、「営業プロセスの見える化」が注目されています。なぜなら、CRMやSFAで蓄積されたデータを活用することでの営業活動の生産性向上が期待されているからです。
「営業プロセスの見える化」とは、営業担当者が「いつ」「どこで」「どのような活動をしているのか」を誰が見ても分かるようにすることです。そして、CRMやSFAなどのITツールの活用において、「営業プロセスの見える化」が必要だからです。
では、なぜCRMやSFAなどのITツールの活用において、「営業プロセスの見える化」が必要なのでしょうか?それは、多くの企業ではCRMやSFAなどのデータを活かし切れず、成果に結びついていないからです。
営業プロセスの過程において、営業担当者が各自の判断で営業課都度を行うと営業活動は属人化し、担当者がいないと営業活動ができない状況となります。また、組織全体として営業活動の現況や課題を正しく把握できないため、経営方針や意思決定などに支障をきたします。営業活動に多くのリソースを割くことができないなかで組織として売上増などの成果に結びつけるためには営業プロセスの見える化を行い、組織全体で最適化することが必要となります。
営業プロセスを見える化するメリット
営業プロセスの見える化にはどのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは営業プロセスの見える化のメリットについて3つ紹介します。
1. 業務を標準化できる
営業プロセスを見える化することにより、優秀な営業担当者のスキルや知見を営業プロセスとして組み込むことができます。これにより組織全体で営業担当者の底上げを図ることができます。また、営業担当者の退職や部署異動などが発生したとしても、後任の営業担当者にスムーズに引き継ぐことができます。
これまで営業活動は属人化されており、営業担当者しか知らない「ブラックボックス」の中で行われることが一般的でした。そのため、担当者不在では顧客対応が満足に行われないなどボトルネックとなっていました。ノウハウやスキルを共有することで他の営業担当者に成果をあげられてしまうと自分の立場の優位性を保てなくなります。このような考えからノウハウやスキルを自分のものにしておきたいと考える営業担当者は多くいます。
しかし、営業プロセスを可視化することで、これまで優秀な営業担当者のスキルやノウハウを共有でき、優秀な営業担当者と同じようなプロセスで営業課都度を行うことができます。
また、営業プロセスの見える化により、「誰がどの案件をどの程度進めているのか?」を正確に把握することができます。このため、営業活動のボトルネックを見つけることが容易になります。
2. 売上目標を立てやすい
営業プロセスの見える化し、「パイプライン管理」を行うことで営業プロセスごとに案件の状況を数値で分かるため受注率などの数値を正確に把握できるようになります。
「パイプライン管理」とは営業プロセスの見える化で定義した各プロセスにおける営業活動を数値化し、状況を管理することです。営業プロセスごとに活動内容と結果をデータとして登録し、歩留まり率(ふどまりりつ)、次のステージへ移行した顧客の数、受注率などのデータを蓄積します。そして、蓄積したデータを分析し、行動量を逆算してシミュレーションを行えば、受注見込みの案件件数、受注時期、売上見込み金額、売上時期などを正確に予測できるようになります。これにより営業マネージャーや四半期ごとや半期ごとの適正な売上目標や営業目標を立てやすくなります。
その一方で組織から与えられた営業目標を実現するための必要な営業計画の作成も容易となります。なぜなら、パイプライン管理で得られたデータを元に営業目標達成に必要な行動量を逆算することで、必要な行動を営業計画への落とし込みが可能となるからです。営業計画への落とし込みの過程の中で「現状の人員では必要な行動量を確保できない」などの課題を発見でき、業務の見直しや人員補充などの対策も準備しやすくなります。
3. タスク管理がしやすい
営業プロセスの見える化をすることでタスク管理を行いやすくなります。
「タスク」とはプロセスの完了に必要な小さな作業単位のことです。営業プロセスにおけるタスクとしては以下があります。
- リード獲得のためのメルマガ発行
- 問合せのあった顧客への電話
- 商談
- 提案
- 受注
- 契約
- その他
営業プロセスを定義する中で「各プロセスの完了条件」や「各プロセスの完了に必要な行動」も合わせて定義します。
タスク管理には営業担当者及び営業マネージャーの立場において、それぞれメリットがあります。
営業担当者は複数の案件を抱えていることが一般的です。そして、複数の案件を同時並行で行うと何から手をつければよいか分からなくなることがあります。しかし「タスク」として必要な作業単位を明確にすることで作業の優先度や期限をつけることができ、作業遅れの防止にもつながります。
また、営業マネージャーは各営業担当者のタスクを把握できるため、各営業担当者の活動状況や期限の遅れなどを把握できます。それに加えて目標達成に向けた行動をチーム全体で行うことができるでしょう。
営業プロセスを構成する要素
営業プロセスを構成する要素には、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは「営業プロセスを構成する要素」について解説します。
1. ワークフロー
「ワークフロー」とは、「Work(仕事)」と「Flow(流れ)」を組み合わせたもので、「一連の業務の流れ(あるいは一連の業務の流れを図式化したもの)」を表す言葉です。具体的には営業担当者が行っている営業活動の流れです。顧客へのコンタクト、商談、受注処理などが該当します。「営業プロセス」とは「見込み客獲得から受注・カスタマーサクセスまでの一連のワークフロー」と捉えることができます。
営業プロセスを整理するにあたっては、営業活動のワークフローを把握する必要があります。しかし、「わが社の営業活動は特殊だから営業プロセスを整理することができない」とお話をする企業があります。
その場合、まずは現状の業務を分析してタスクを洗い出し、各プロセスに当てはめて整理するとよいでしょう。
2. 数値指標
数値指標とは、具体的には見込み客の獲得数、顧客訪問数、受注額、売上額などです。
営業プロセスを構成する要素としてはワークフローの各フェーズにおける数値指標が必要です。「計測できないものは管理できない」という言葉があるように、各営業プロセスの現況を正しく把握するためにも数値指標を明確にすることが必要です。
まずは以下の2つの対策を検討します。
- それぞれの営業プロセスを管理するための数値を決める
- 指標を策定するために必要なデータを入力する
とはいえ、いきなり営業担当者に決めた数値指標とデータの入力を依頼したとしても反発されることが予想されます。このため、まずは参考情報として現状を把握することを伝えるとよいでしょう。
営業プロセスを見える化する手順
営業プロセスを見える化するためには、以下の手順が必要です。
- 売上など、達成したい目標を決める
- 既存の営業プロセスの課題を把握する
- 目標とプロセスを照らし合わせてブラッシュアップする
- 誰がどのプロセスを担当するか役割を決める
- CRMなどのシステムに組み込む
それぞれの具体的な内容を以下で解説します。
1. 売上など、達成したい目標を決める
「パイプライン管理」による効果を創出するためには、各フェーズごとに達成したい目標を決める必要があります。なぜなら、目標(KPI)と実績と比較して差異分析を行うことで課題が明確になり、対策を立てやすくなるからです。
営業活動における目標値として用いられる項目には以下のものがあります。
- コール数
- アポイント数
- アポイント獲得率(アポイント数÷コール数)
- 新規アポイント数
- 新規アポイント率(新規アポイント数÷アポイント数)
- 商談数
- 商談化率
- 受注件数
- 受注率
これらの項目についてまずはそれぞれ目標数を決めます。そして、日々の営業活動において実績値を入力しながら週1回の単位で目標と実績の差異を確認します。そして、「なぜ差異が生じたのか?」と分析を行うことで課題を見つけ、業務改善につなげることができます。また、再分析を行うことで、営業マネージャーは各営業担当者に改善に必要な行動を促すこともできます。
また、各フェーズごとの顧客数とCVRを見える化することも大切です。なぜなら現在のフェーズから次のフェーズに移行した顧客数を把握することで、「それ以外の顧客はなぜ当フェーズで離脱したのか?」といった分析を行うことができるからです。
これらの分析を行うためにも、まずは達成したい目標を決めましょう。
2. 既存の営業プロセスの課題を把握する
既存の営業プロセスの課題を把握するためには営業担当者にヒアリングを行い、現状を把握することが必要です。営業担当者からのヒアリング結果を踏まえ、それぞれのプロセスで言語化し、まとめます。そしてまとめた結果と既存の営業プロセスとを比較することで乖離の発見につながります。見つかった乖離は現状とそぐわない部分かもしれません。
また、経営課題の解決や戦略実行に伴い、既存の営業プロセスではそぐわない部分が出てくるかもしれません。このような場合は営業プロセスの見直しが必要となります。このように既存の営業プロセスとの乖離やそぐわない部分が課題として抽出されます。
3. 目標とプロセスを照らし合わせてブラッシュアップする
このステップでは2つめのステップで抽出した課題を検討し、既存のプロセスを照らし合わせてブラッシュアップします。2つめのステップで抽出した課題は、1つめのステップで決めた目標を達成するための阻害要因となっているものです。そして目標を達成するためには、これらの抽出された課題を解決する必要があります。
例えば、「トップの営業担当者と一般の営業担当者では受注率が異なる」という課題が営業担当者のヒアリングで分かったとします。このとき、「なぜ受注率が異なるのか?」といった分析が必要です。仮にその要因が「トップの営業担当者と一般の営業担当者では顧客ニーズの把握に差があり、結果、顧客に刺さる提案ができていない」とします。このとき、「トップの営業担当者のように顧客ニーズを把握できるよう、営業プロセスをブラッシュアップすることが必要」という対策が考えられます。具体的には、「トップの営業担当者が確認している項目をまとめ、一般の営業担当者でも使えるようなヒアリングシートを用意する」などです。
このように、目標とプロセスを照らし合わせてブラッシュアップすることで、目標達成の確度が高まります。
4. 誰がどのプロセスを担当するのか役割を決める
営業プロセスの定義において、それぞれのプロセスの内容はもちろん、誰がどのプロセスを担当するのかという役割を決めることが必要です。そうしなければ、タスクの抜け漏れや作業を行う担当者の不在につながりかねないからです。
例えば、
- 見込み客獲得
- 担当:マーケティング部門
- 役割:見込み客獲得
- ナーチャリング
- 担当:インサイドセールス部門、あるいは営業部門
- マーケティング部門が獲得したリードの購買意欲をさらに高め、営業部門にパスする
- 商談
- 担当:フィールドセールス部門、あるいは営業部門
- 顧客との商談進行
- 受注
- 担当:フィールドセールス部門、あるいは営業部門
- 顧客からの受注獲得及び契約締結
- フォロー
- 担当:カスタマーサポート部門
- 役割:契約の継続、アップセルやクロスセルにつなげる
また、「それぞれのプロセスで何をするのか?」という行動も定義することも必要です。例えば「顧客からの問合せ時にはインサイドセールス部門から案内の電話をかける」などです。
このように「誰がどのプロセスを担当するのか役割を決める」ことで営業プロセスの全体像を俯瞰できるようになります。
5. CRMやSFAなどのシステムに組み込む
営業プロセスの見える化を実現するためには情報をリアルタイムで更新・共有する仕組みが必要です。そのためにはCRMやSFAなどのITツールの活用が必須です。
CRMとは「顧客関係管理」のことで、自社と顧客との関係性を管理します。具体的には「顧客先」「担当部署」「担当者名」「役割」などです。各営業部門あるいは営業担当者ごとに管理していた顧客に関する情報を一元管理することで、適切に顧客にアプローチできるための土台を整えます。
また、SFAとは「営業支援システム」のことで、営業活動の履歴や案件を通じた顧客との関係性を管理します。具体的には「過去の商談の進行状況や結果(受注/失注)」、「失注に至った理由」などです。商談結果を管理することで、次回の案件獲得に向けた活動の土台を整えます。
フェーズ、管理項目、レポートなど、先に定義した内容をこれらのシステムに反映し、各営業担当者がデータを入力することでリアルタイムで状況を把握できる仕組みを整えます。
なお、CRMの構築や整備を進めるにあたっては、CRMに関する知識や経験を必要とする場面も多いので、専門のコンサルタントの知識や経験を上手く活用しながら進めるとよいでしょう。
まとめ
この記事では営業プロセスの見える化とメリットや見える化の手順を解説しました。
営業プロセスの見える化とは、見込み客との最初の接点から受注、アフターフォローに至るまでの営業活動を構成する一連のプロセスを明確にすることです。営業プロセスの見える化により、「業務の平準化」「売上目標を立てやすい」「タスクを管理しやすい」などのメリットがあります。
また、営業プロセスの見える化を行う手順として、「目標を決める」「既存の営業プロセスの課題の把握」「営業プロセスのブラッシュアップ」「役割の明確化」「システムへの組み込み」です。
営業プロセスの見える化は組織の営業力強化に欠かせない要素です。組織として成果をあげるためにも、是非、営業プロセスの見える化に取り組んでみてください。